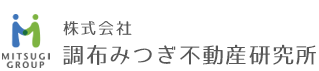DATE: 2018-09-16
【民法改正】Part1
貸室設備等の不具合による賃料の減額のガイドライン
2020年4月から施行される約120年ぶりの民法改正に伴う改訂で、大きな変更点が「貸室設備等の不具合による賃料の減額のガイドライン」の項目の新設です。
改正民法では、貸室の設備などに雨漏りなど借主に責任のない不具合が生じて居住できなくなった場合、賃料は居住できなくなった部分の割合に応じて当然に減額されると定めています。
従来は「減額請求できる」との表現だったが、改正民法では「当然減額」と改められました。
しかし、賃料がどの程度まで減額されるかについては明確な基準を定めていないため、日本賃貸住宅管理協会では、不具合のケースごとに減額の基準と割合をまとめ、賃貸借契約書の解説に加え、ガイドラインでは、電気・ガス・水道の不具合をA群。トイレ・風呂・エアコン・テレビなどの通信設備の不具合と雨漏りによる利用制限をB群に分類。
まず不具合がA群に該当するかを確認し、該当すればA群の賃料減額割合と免責日数を基準に日割りで金額を算出する。
A群に該当しない場合はB群に該当するかを確認し、同様に金額を算出する。
台風や震災などの天災が原因で、貸主・借主の双方に責任がない場合も、賃料の減額認められる。

※日管協:居住用建物賃貸借契約書より抜粋
【例1】
月額賃料10万円
ガスが5日間使えなかった場合
免責日数3日=減額対象日数2日
100,000円×10%×2日÷月30日=約666円
【例2】
月額賃料7.5万円
お風呂が7日間使えなかった場合
免責日数3日=減額対象日数4日
75,000円×10%×4日÷月30日=1,000円
賃料減額ガイドラインはあくまで計算の目安であり、必ずこれに沿って減額しなければいけないということではないが入居者が不意の事態に陥った場合も安心して生活を送れるよう基準を明確にしたものである。
このガイドラインが施行されると、管理会社としては今まで以上に設備系トラブルの未然防止が必要になります。発生ベースでの対応ではお客様にも大家さんにも迷惑がかかってしまう可能性があります。
昨今、テナントリテンション(長期入居)が叫ばれている賃貸業界では、いかに入居者様に満足して住んでもらうかが課題になっています。
一見大家さんに不利に見えるこのガイドラインも、見方を変えるとこれがあることによって安心して長く住んでもらえるので大家さんにも十分メリットはあるのかと感じています。
<補足>
以前お風呂が故障して銭湯代を支払ったことがありましたが、上記に当てはめると、460円×4日分で1,840円とガイドラインより高くつきますね。